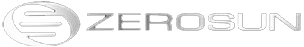- ZEROSUN TOP
- NEWS
- ニュース一覧:年月
- ホンダ、満を持して軽EVを発売へ
ホンダ、満を持して軽EVを発売へ
コラム
(2025/09/18)9月12日、ホンダが電気自動車(EV)の軽自動車である「N-ONE e:」の発売を開始した。同社は、エンジンを搭載する軽自動車の販売において「N-BOX」が圧倒的なシェアをキープしているが、その得意とする市場にEVを投入するに至った。その狙いとは?
・”先輩”軽EVにはどんなクルマが?
現在、日本の自動車メーカーとして軽自動車のEVを販売しているのは、3社。日産が「サクラ」、三菱自動車が「eKクロスEV」をリリースしており、ホンダは「N-ONE e:」の販売に先立ち、軽バンの「N-VAN e:」をラインナップしている。自動車メーカーが多数ある日本において、大手メーカーが製造する軽EVがまだ片手で足りるほどの車種しかないことも驚きだが、EVにマストな充電等、さまざまな条件を考慮しても、コンパクトかつ車両価格が手頃な”普通の”軽自動車に軍配があがっても仕方ないように思う。
なお、クルマ好きの読者ならもうお気づきだと思うが、サクラとeKクロスEVは”兄弟車”。基本的なメカニズムをシェアしており、日産と三菱の共同開発によるものだ。一方、今回「N-ONE e:」をリリースしたホンダだが、ひと足先にデビューさせた「N-VAN e:」は軽バンとは名ばかりに、見た目はよく見かけるワンボックスタイプの軽自動車であり、同社の「N-BOX」をはじめとする「N」シリーズのメンバーだ。デビューは昨年10月。軽バンと聞けば、商用に用途が限定されるように思うがそんなことはない。室内は広い空間が確保されており、ビジネスは当たり前のこと、キャンプなどのアウトドアはじめ幅広いレジャーに対応する車両として活用が期待できるものだ。
・国内普及を目指して
日本にはじめて軽EVが登場したのは、2009年。三菱が「i-MiEV」を発売した。当時、車両価格は400万円半ばという高価格。外車が購入できる価格設定だった。だが、2021年に生産を終えるまでにおよそ2万台が市場に出たとされる。それから2022年になると、日産と三菱がそれぞれサクラとeKクロスEVをリリース。このとき価格が200万円台となり、需要が広がったとされる。今年7月までにおよそ10万台が売れた。そんななか、もともと軽自動車に定評あるホンダが本腰を入れたことで国内外の他メーカーも自ずと意識しないわけにはいかなくなってきた。2025年度中には、トヨタ・ダイハツ・スズキの企業連合が開発した軽バンEVの登場も予定されているという。
さて、新たにお目見えした「N-ONE e:」は、名前から想像できるように、同社の「N-ONE」をベースに電動化した車両。軽としては最長の航続距離となるおよそ300km走行を実現させている。これまで200km弱であった航続距離を大幅に延伸することとなった。この距離であれば、日常における通勤、買い物も十分にクリアできる性能が確保でき、ちょっとした週末のプチドライブにも対応可能といえるだろう。
同社ではターベットとして40~50歳代の女性を想定しているとのこと。これにはやや驚きを感じるが、頻繁に乗車せず、また高騰が続くガソリン代を少しでも抑えたいというニーズを持つ世代を設定したのかもしれない。車両本体価格は269万円からとなるが、そこはエコカーに対する国からの補助金として約57万円が出るため、実質212万円台からの購入が可能となる。
中国のように国家産業としてEV製造に注力しているわけでもなく、欧米と比較してもまだまだガソリン車やハイブリッド車の人気が高い日本国内。積極的にEVを購入するのは、ラグジュアリーなハイブランドというイメージも強い。ゆえになかなか浸透せず、EV市場は停滞気味と言われている。そんななか、軽自動車に目をやると、一家につき複数台車両を保有する郊外や地方での戸建ての居住者の需要が高く、その場合、家庭内での充電が可能となる。都市部では集合住宅での住まいも少なくないために充電設備の確保がハードルとなってしまうが、少し走って給油しに行かなければならないガソリンスタンドに出向くよりも、自宅で充電できるという利便性をアピールすることができるというわけだ。日本国内の新車販売を考えた場合、全体のおよそ3割が軽自動車となっているだけに、消費者に幅広い選択肢を与えることになりそうだ。地球温暖化等、私たちを取り巻く環境が徐々に変化し、街を走る自動車にもこれからさまざまな変化が訪れるようになる。よりスマートなカーライフを追求するにあたり、軽EVという選択も十分に考慮されるようになるのではないだろうか。
普通車の国産EVが思うように普及しない日本国内において、EVに乗ってみたいという消費者にとっては、200万円台でユーザーになれる軽EVはおすすめしやすい。近年は内装等でフル装備した軽自動車などは価格も高い。これに対し、軽EVは国の補助金に加えて別途自治体が補助金を交付しているため、合算すれば軽EVのほうがお手頃に購入できるケースもある。当然ながら、”エコカー”として重量税や軽自動車税の減税も受けることが可能のため、オトクなメリットも多いといえる。が、やはりネックとなるのが所有者の住環境になりそうだ。まだまだインフラ設備が整っておらず、どこに充電設備が用意されているかを事前に調べて走行する必要がある。今回の新車投入が国内における軽EVの普及に一石を投じることになるのか、今後の動向が気になるところだ。